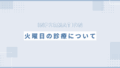歯を失う原因の第1位といえば「歯周病」。
日本では成人の約8割が何らかの歯周病にかかっているとも言われており、まさに“国民病”ともいえる存在です。
歯周病は、歯ぐきが腫れたり、出血したりするだけでなく、進行すると歯を支える骨が溶けてしまい、最悪の場合、歯が抜けてしまう病気です。
しかも、糖尿病や心疾患、認知症など、全身の健康にも影響を与えることがわかってきています。
そんな歯周病ですが、実は「日々の生活習慣」によってリスクが大きく左右されるのをご存じですか?
今回は、歯科医師の視点から「歯周病リスクを高めるNG生活習慣」を7つご紹介します。
1. フロス・歯間ブラシを行わない
歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れの約6割しか落とせないと言われています。
特に歯周病の原因となるプラーク(歯垢)は、歯と歯の隙間に溜まりやすく、放置すれば歯ぐきの炎症を引き起こします。
フロスや歯間ブラシを併用することで、歯周病予防の効果は飛躍的にアップします。
一日一回、夜だけでも構いませんので、習慣化してみてください。
2. 喫煙習慣がある
タバコは歯周病の最大のリスク因子のひとつです。
ニコチンや一酸化炭素などの有害物質が歯ぐきの血流を悪くし、免疫力を低下させることで、歯周病菌が活動しやすい環境を作ってしまいます。
さらに、喫煙者は歯ぐきの炎症に気づきにくく、発見が遅れる傾向があります。
もし禁煙が難しい場合でも、歯科で定期的なチェックを受けることが非常に重要です。
3. 甘い飲み物をダラダラ飲む
糖分は虫歯だけでなく、歯周病にも影響を与えます。
甘い飲み物(ジュース・缶コーヒー・スポーツドリンクなど)を長時間にわたって口にすることで、口腔内が酸性に傾き、細菌が増殖しやすくなります。
間食や飲み物は、時間と量を意識することがポイントです。
水やお茶を基本にして、甘いものを摂ったあとはうがいや歯磨きでケアしましょう。
4. ストレスをためがち
意外に思われるかもしれませんが、ストレスも歯周病リスクを高めます。
強いストレスが続くと、免疫力が低下して歯ぐきの炎症が起きやすくなるほか、歯ぎしりや食いしばりを引き起こして歯周組織を傷めてしまうことも。
リラックスできる時間を意識的に作ることも、歯の健康を守る大切なポイントです。
趣味や運動、睡眠など、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。
5. 歯科健診を受けない
「痛みがないから大丈夫」と思っていませんか?
実は、歯周病はかなり進行するまで自覚症状が出にくい病気です。
歯ぐきの腫れや出血、口臭など、症状が現れたときにはすでに中等度〜重度になっているケースも多いです。
歯科医院での定期的な健診とクリーニングは、歯周病の早期発見・予防に効果的です。
少なくとも半年に1回は、プロの目でチェックしてもらいましょう。
6. 食生活が偏っている
歯ぐきの健康を保つには、バランスのとれた食生活が不可欠です。
特にビタミンC・ビタミンD・カルシウムなどは、歯ぐきや歯を強くするために大切な栄養素です。
カップ麺やファストフードなど、栄養が偏った食事ばかりでは、口の中の細菌バランスも崩れやすくなります。
和食中心の食生活や、野菜・魚・発酵食品などの摂取を心がけましょう。
よく噛むことで唾液が分泌され、口腔内の自浄作用もアップしますよ。
毎日の習慣が歯ぐきの未来を左右します
今回は、歯周病になりやすくなる7つのNG生活習慣をご紹介しました。
- 起きてすぐの歯磨きをサボる
- フロス・歯間ブラシを使わない
- 喫煙している
- 甘い飲み物を長時間飲む
- ストレスをためている
- 歯科健診に行かない
- 食生活が偏っている
ひとつでも当てはまった方は、今日から少しずつ見直してみてください。
歯周病は「予防」が何より大切です。
正しい習慣を身につけて、大切な歯をいつまでも健康に保ちましょう。
気になる症状がある方、しばらく歯医者に行っていないという方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。