「歯磨き粉に含まれるフッ素ってなに?」
「フッ素は毒だと聞いたことがあるけれど、本当に使って大丈夫なのだろうか?」
そんな疑問や不安を抱えている患者さんは少なくありません。
とくに最近では、ナチュラル志向やオーガニックを好む方も増えており、「なるべく添加物を避けたい」という考え方もよく耳にします。それ自体はとても自然で素晴らしい感覚だと思いますが、誤った情報に振り回されてしまうことで、健康を守るための正しい選択肢を見逃してしまっている方がいるのも事実です。あふれる情報の中で、何を信じればよいのか迷ってしまうこともありますよね。
そこで今回は、歯磨き粉に含まれているフッ素について、歯科の専門的な視点から、医学的根拠に基づいた情報をもとにわかりやすく解説していきたいと思います。
フッ素ってなに?どんな働きをするの?
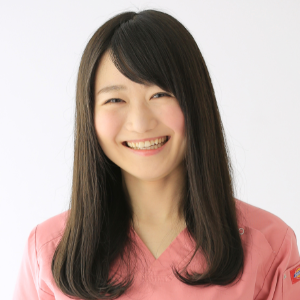
まず、フッ素とは自然界に存在する元素のひとつで、単体では非常に反応性が高いため、実際には他の元素と結びついた「フッ化物」として存在しています。私たちが日常的に使用する歯磨き粉に含まれているのも、この「フッ化物」です。
実は、フッ化物は特別な化学物質というわけではなく、私たちが日常的に口にしている食べ物や飲み物の中にもごく自然に含まれています。たとえば、お茶や野菜、果物、魚、肉、卵、水道水など、私たちが毎日食べているものの中にも微量ながらフッ化物が含まれています。
世界保健機関(WHO)も、フッ化物を人間にとって必要な微量栄養素のひとつと定義しており、世界中でその有用性が認められています。
歯磨き粉のフッ化物はどんな効果があるの?
歯磨き粉に含まれるフッ化物には、4つの重要な働きがあります。
- 再石灰化促進
- 脱灰の抑制
- 結晶性の改善
- 細菌の代謝阻害
主に、初期のむし歯の修復を助ける「再石灰化の促進」、酸によって歯が溶けるのを防ぐ「脱灰の抑制」、歯の構造そのものを強くする「結晶性の改善」、そしてむし歯の原因となる細菌の活動を抑える「細菌の代謝阻害」という4つの効果です。
簡単に言えば、歯を強くし、むし歯菌が酸を出すのを抑え、歯が溶けるのを防ぐという、非常に頼もしい存在なのです。
さらに、1日1回の歯磨きよりも、2回以上歯磨きをすることでむし歯の発生を抑えるという研究結果もあります。2回と3回では効果に大きな差は見られなかったことから、1日2回以上の歯磨きを習慣にすることが大切です。
ただ、フッ化物は万能ではなく、使っていれば絶対にむし歯にならないというわけではありません。大切なのは、フッ化物をうまく取り入れつつ、食生活の見直しや正しいブラッシングなど、日々の生活習慣もあわせて意識することです。
使いすぎると危険?フッ素中毒とは
一方で、フッ化物に関して「急性中毒」や「フッ素症」といった言葉を耳にして心配される方もいます。たしかに、どんな物質でも過剰に摂取すれば体に悪影響を及ぼします。塩や醤油でも同じですよね。フッ化物も、過剰に摂取すれば急性中毒やフッ素症のリスクがありますが、日常的に歯磨き粉を使う範囲では心配はいりません。
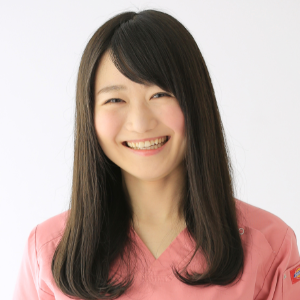
まず、フッ素とは自然界に存在する元素のひとつで、単体では非常に反応性が高いため、実際には他の元素と結びついた「フッ化物」として存在しています。私たちが日常的に使用する歯磨き粉に含まれているのも、この「フッ化物」です。
- 歯が生えてから5歳までは950ppmを使用する
- 6歳以上は大人と同様に1450ppmを使用する
- 使用量の見直し(米粒、グリンピース、ハブラシ全体)
→参考文献を参照
子どもの場合、3歳までは950ppmの歯磨き粉を「すりつける程度」で、3〜5歳は「グリンピース大」、6歳以上になると1450ppmの歯磨き粉を大人と同じように使用することが推奨されています。
また、歯磨き後のうがいはしない、または少量の水で1回だけにすることで、フッ化物の効果が口の中にとどまりやすくなります。もし誤って大量に飲み込んでしまった場合には、まず牛乳を飲ませてフッ化物の吸収を抑え、そのうえで医療機関を受診するようにしましょう。
世界基準となった日本のフッ化物使用法
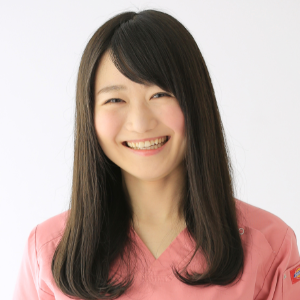
日本でも、ようやく2023年に歯磨き粉に含まれるフッ化物の濃度が見直され、世界基準に近づきました。これにより、フッ化物の効果がより発揮されやすくなっています。
特にむし歯のリスクが高い方や、再発を繰り返している方、唾液量が少ない方、矯正装置や補綴物が入っている方には、フッ化物配合のうがい薬などの併用もおすすめです。さらに、歯科医院で定期的に行うフッ化物塗布は、むし歯になりやすい部分を集中的に守るのに効果的です。
大切なのは、正しい知識をもって、適切に使うこと。フッ化物を正しく使えば、むし歯予防に大きな力を発揮してくれます。「自分にはどの濃度や使い方が合っているのか知りたい」「子どものむし歯予防にどう活用すればいいのかわからない」など、不安なことがあれば、ぜひお気軽に歯科医院で相談してくださいね。
引用・参考文献
- ・4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法(2023)
https://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/news/2023/news_230106.pdf - ・伊藤直人, 『カリエスブック』, 医歯薬出版, 2022
- ・伊藤直人, 『齲蝕の削らない治療を担う歯科衛生士のためのカリエスコントロール5つのレシピ』, 医歯薬出版, 2025


